- 2018-11-17
- Artwork (芸術作品)
- コメント:1件

日本と西洋では宗教観の違いがあるため、時には思わぬギャップが生まれやすいもの。
例えばルーベンスの「ローマ慈愛(Roman Charity)」の様に、作品名だけを聞くと、とても教訓的に思えるのに。でも実際に作品を目にすると、気持ち悪さというか、違和感を感じてしまう…様な。
私としては、こういうギャップを味わうのも宗教画の一つの楽しみ方だと思っています。もちろん前提として、背景の知識は必要ですが。
|
【 目次 】 ・ルーベンスの「ローマの慈愛」を見てみよう! |
今回は巨匠ルーベンスの「ローマ慈愛」について、私なりの解釈も踏まえて解説していこうと思います。
ルーベンスの「ローマの慈愛」を見てみよう!

「ローマの慈愛(キモンとペロ)」(1612年)ピーテル・パウル・ルーベンス
・141×180cm、カンヴァスに油彩、エルミタージュ美術館所蔵
これはルーベンスの「ローマの慈愛」で、娘ペロが父親キモンに母乳を与えている場面を描いた作品です。
ちなみにタイトル名「Roman Charity」を日本語に訳すと、”ローマの慈愛”もしくは”慈悲”になりますが、ここでは”ローマの慈愛”で話を進めていこうと思います。
さて早速質問ですが、”この作品を観て、あなたはどう感じましたか?”
慈愛に満ちた素晴らしい絵だ!と思います?
それとも、気持ち悪さを感じましたか??
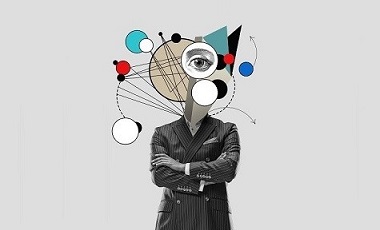
私の考えでは、別にどちらの解釈も間違っていないと思います。
というのも、宗教観や文化の違いが大きいと思うから。価値観が違えば、解釈が違ってくるのも仕方がないですしね。
日本人からすると、肉親に母乳を与えるという行為は、考えようによっては近親相姦(きんしんそうかん)とも受けとられるだろうから。気持ち悪さや違和感を覚えるのも無理はありません。
大事なのは、こういった考えもあるんだな~と受け入れる事でしょうか。
実際私が「ローマの慈愛」を初めて観た時も、ちょっと違和感を覚えたほどですから。

「ローマの慈愛(キモンとペロ)」(1620‐25年)ピーテル・パウル・ルーベンス
・194×200cm、カンヴァスに油彩
宗教観の違いから生まれるギャップを味わうのもオモシロイですが、これだけで終わるのも勿体ない。
私の持論にもなりますが、宗教画には他にも魅力があると思うから!
その楽しむ秘訣として重要なのが”宗教や背景の理解に尽きる!”と思っています。
次では、もうちょっと深堀して「ローマの慈愛」について解説していこうと思います。
ローマの慈愛(Roman Charity)について解説します!
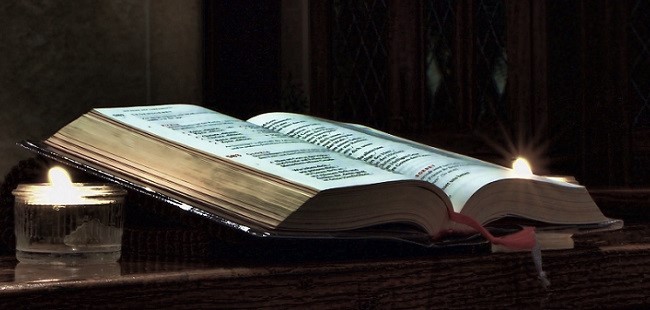
先ほどちょっと触れましたが、「ローマの慈愛」は娘ペロが父親キモンに母乳を与えている場面を描いた作品で、現在では”道徳的模範”として考えられている程です。西洋の価値観を理解する上でも、非常に重要な主題というわけですね。
ここでは参考として、『西洋美術解読事典』の一部分を取り上げて説明しようと思います。
キモンとペロ
…「ローマの慈愛」はキモンとペロの故事をさす。
キモンは牢獄で処刑の日を待つ老人で、それゆえ全く食物を与えられていなかった。看守はキモンの娘ペロが彼を訪ねることを許した。彼女は父親に自分の乳房を吸わせて栄養を与えた。場面は牢獄の独房で、手錠をされた白髪の囚人が若い婦人の膝によりかかり、婦人は彼に乳を与えている。看守が鉄格子の入った窓からのぞいている。あるいは死刑執行人が、剣を手にして独房に入ってくる。バロック期の作例は、単なる若さと老いの寓意画のことが多い。性的な意味が強調されることもしばしばである。18世紀後半の新古典主義の時代には、本来めざしていたところの孝行の道徳的模範として取り上げられた。
・出典元:『西洋美術解読事典』の一部
「ローマの慈愛」という話は、キモンとペロの故事が元ネタになっているそうです。

「ローマの慈愛(キモンとペロ)」(1630年)ピーテル・パウル・ルーベンス
・155×190cm、カンヴァスに油彩、アムステルダム美術館所蔵
そしてもっと興味深い点は、”性的な意味が強調される事もあった。18世紀後半は、孝行の道徳的模範として取り上げられた”と。
時代によって解釈が異なっていたというのが、何とも興味深い点ですね!
僕らが「ローマの慈愛」を見て、教訓的だ!と感じようが、逆に気持ち悪く卑猥だ!と思おうが、どちらも間違った解釈ではないわけです。西洋でも時代によって解釈も違っていたわけですから。
こういう考えもあったんだ~と、広い心で受け入れる事が大事なんでしょうね。
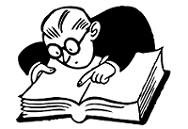
ちなみに”慈愛”という用語を辞書で調べると、”恵みを与え、苦を取り除く事。または、その心。”という意味になるそうです。
まさに「ローマの慈愛」に描いているシーンそのものだと思いませんか?
他の「ローマの慈愛」を描いた作品を挙げてみました。

「ローマの慈愛」は西洋画でもよく描かれる主題の一つ。ここまでルーベンスの作品を3点挙げてきましたが、実は多くの画家も描いている題材だったりします。
ここでは、代表的な画家としてジャン=バティスト・グルーズやルイ=ジャン=フランソワ・ラグルネ。それから今回初めて聞いた名ですがパウルス・モレールスの作品を紹介したいと思います。

「ローマの慈愛(キモンとペロ)」(1633年)パウルス・モレールス
・147.5×162cm、カンヴァスに油彩、スコットランド・ナショナル・ギャラリー所蔵
構図的にはルーベンスの「ローマの慈愛」と似ています。
ただ大きく違うのは、娘ペロと父親が見つめ合って描かれている点でしょうか。より娘の”慈愛”に満ちた感じが伝わってきますよね。

「ローマの慈愛(キモンとペロ)」(1767年頃)ジャン=バティスト・グルーズ
・65.4×81.4cm、カンヴァスに油彩
こうやって見ていくと、全く気持ち悪いとか卑猥には感じられない。18世紀頃になると道徳的な模範として見られていたのも、何となく分かる気がします。

「ローマの慈愛(キモンとペロ)」(1770年)ジャン=バティスト・グルーズ
・24.5×32.5cm、カンヴァスに油彩、ルーヴル美術館所蔵
さらに「ローマの慈愛」という話は、紀元1世紀にはすでに存在していたようです。ポンペイのフレスコ画で描かれているのが分かっていて、調べれば調べるほど面白いな~って思いますね。

「ローマの慈愛(キモンとペロ)」(1782年頃)ルイ=ジャン=フランソワ・ラグルネ
・62×73cm、カンヴァスに油彩、オーギュスタン美術館所蔵
これまでに多くの画家によって描かれてきた主題ですが、どれも違った描かれ方をされているのはオモシロイですね。
時代によって「ローマの慈愛(慈悲)」は、様々な解釈がされてきたわけですが、画家も画家なりの解釈でカンヴァスに表現したって事でしょうか。
見れば観るほど面白い「Roman Charity」。
ぜひ美術館で見かけたら、今回の話を思い出してみてほしいと思います。
※ここで扱っているイラストや作品画像はpublic domainなど掲載可能な素材を使用しています。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。


















娘さんすごいなあ